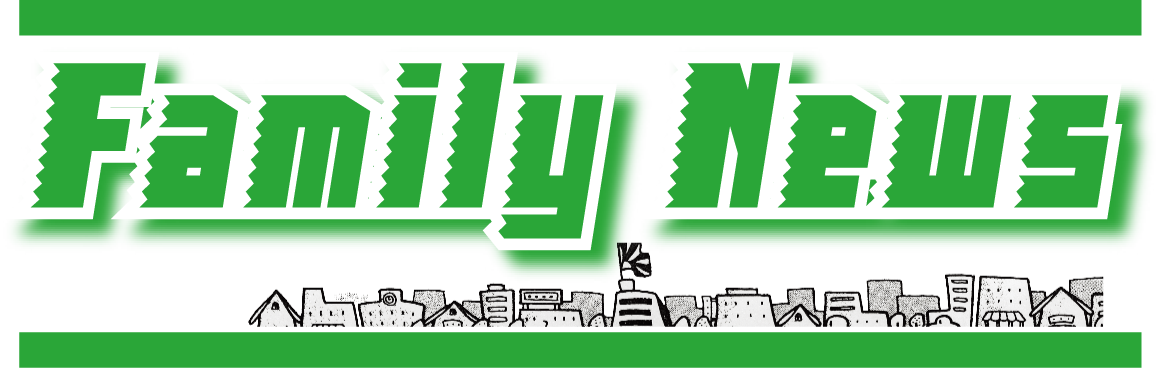肝に銘じた誤報問題からの教訓
「原因はまず、担当記者に思い込みがあったことだった」
読売新聞が8月30日、27日に1面トップで報じた記事について、「重大な誤報」だったとして、取材の経緯を検証した結果です。組織としての「裏付け」も不十分のまま報じたと謝罪しました。
同じ記者としてひとごとではありません。もう20年以上も前です。警察が秘密裏に省庁幹部を捜査しているとの情報をつかみました。周辺取材を積み重ね、疑惑の核心に迫っている気になりました。
しかし、結論からいえば、取材の方向が間違っていました。逮捕されたのは別の省庁幹部です。ぎりぎりで誤報を免れたのは、非公式な取材で、ある捜査員から見立ての誤りを指摘されたからでした。
自分の考えに近い情報は耳に心地良く、次々と集まってきます。関心分野の情報が次々と表示されるSNSのようです。興味のない情報はつい遠ざけてしまいがちです。だからこそ記者の取材では、何度も立ち止まって真偽を確かめる必要があるのです。
各報道機関は何重ものチェック体制を築いてきました。それでも誤報は絶えません。最近は人工知能などを活用して、校閲の目を増やそうとしています。
インターネット上では情報が瞬時に流れます。真偽を確かめるための時間もまた瞬間です。そんな時代が加速すればするほど、報道にはいっそうの正確な情報発信が求められます。
秋の新聞週間にあたり、記者の一人として、肝に銘じました。
朝日新聞立川支局員 山浦 正敬